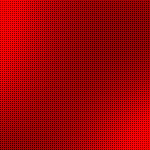食べ残しはダメ、金払ってるんだから自由だろ、という話を読んで。
見栄えのために食べきれないような大盛りや不要なメニューを頼んだりはいいことではないと思いますが、もし自分が流行らない飲食店を経営していたら、残してもいいので大量に頼んでもらえるとありがたいかも、という考えになってしまう想像はつく。売り上げが上がるのです。背に腹はかえられません。
それに見栄え重視のそういう店もありますよね。
自分の個人的な問題としてだけど、摂食障害があった身としては飲食店の量が多すぎて食べられないということがあるのよね。真面目なので残してはいけないという考え方がプレッシャーにもなっていたし、今もそれは残ってます。
食べられなくてハンバーグを持ち帰ったこともあったけど、以前はそもそもが飲食店には入らなかった。
でも大盛り店らしいけど試しに入ってみたい店はありました。注文した以外にも頼んでみたいメニューがあるという人もいると思います。写真映えでなく、純粋にたまにしか行けないから味を知りたいという。もちろん、また今度の楽しみにするのが正式なのかもしれませんが。
何もない田舎というのは外食が一つのエンターテイメントですからね。大人しく家で食ってろと言われてしまえばそれまでですが。
もちろん店によっては最初から持ち帰りは別で頼んだりできますが、想定外に量が多くて食べれきれなかった時の「お持ち帰り文化」がもっと定着すればいいのにと思います。
食中毒の責任とか色々とうるさいことはあると思うけど、「残してはいけないプレッシャー」がなく気軽に注文でき、万が一残ってしまっても持ち帰れるとうれしい。すぐ帰って冷蔵庫に入れられない場合は仕方ないけど。
それか少量でサーブして、お代わりする方式もいいですよね。店側は大変なので形態は限られると思いますが。
自分の腹の具合がわからないのかということになってしまうけど、食べ始めると意外と食べられたとか、今日は突然調子が悪くなったとか、常に体調万全でもないし色々あります。特に精神的な調子に左右されることもあるんですよ。
当然ながらビュッフェ、バイキング形式で残すのはアホだと思いますが。(何度も取りに行けばいいから。ただ満席だと、お一人様には席を空けるのが難しい場合がある)
例外を言い出すとあれだけど、それとは別に訳あって残さざるをえない場合もあることはあります。お店の人に「済みません食べきれなかった」と伝えたとき、嫌な感じを受けたことはないけどね。
私は他人の考え方はどうでもいいし変えようとも思わないんだけど、「金払ってるからいいだろ」が今イチな理由は、例えば肉を残すとその分動物を屠殺しないといけないでしょ。だからダメなんですよ。
動物は木の実みたいに食べられて種が運ばれてという生存戦略じゃないですし。
とにかく、私は自分が気兼ねなく外食を楽しむためにも「お持ち帰り文化」が根付いて欲しい。
テイクアウトもいいのですが、食べ残しを持ち帰る方ね。あと冷蔵より冷凍庫の方を大きめにして欲しい。とりあえず凍らせておけば何とかなるから。
-- 記事一覧ページへ --