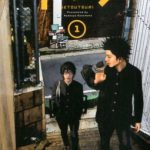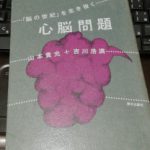上巻が狩猟採取から農耕(穀物の奴隷だとさ)へという流れなのに対し、下巻は近代というか中世以降がメイン。
宗教、科学革命、資本主義、産業革命など。それによって文明は人を幸せにしたかという考察がなされる。
訳者の方のあとがきが、サピエンス全史全体を通した内容を網羅していて、ざっと内容を知りたい場合はそちらを参考にすれば良さそう。7ページくらいなので。
その部分をお借りしてちょっとまとめる。
なぜ現生人類(ホモ・サピエンス)が地球を支配するに至ったのか
→多数の見知らぬものどうしが協力し、柔軟に物事に対処する能力を身に付けた
→(ハチやアリも多数が協力するが、それは近親者に限られるし進化でプログラムされており柔軟性を欠く)
そのサピエンスならではの能力を可能にしたもの
→想像力
→約7万年前の認知革命を経て虚構、架空の事物について語れるようになった
→伝説、神話、神々、宗教など、それを共有する者なら誰もが協調できる。
→企業、法制度、国家、人権や平等も同様のものであり、作り変えればすぐに行動パターンや社会構造を変更できる。(他の動物のように遺伝子や進化に束縛されない)
農業革命-一万年前
→爆発的に人口が増えた
→原動力として、貨幣と帝国と宗教(イデオロギー)という秩序
→特に「貨幣」は最も普遍的で効率的な相互信頼の制度
科学革命-500年前
→自らの無知を認めることからスタート(それまでは賢者が全て知っているという考え方)
→知識の追求。帝国主義と資本主義がエンジン(政治と経済)
→将来はパイが拡大する(富の総量が増える)と信じるようになる
生物種としてのサピエンスは大成功
→個々のサピエンスの幸福が増したとは言えない
→しかし、暴力はなくなってはいないが、現代はかつてないほどの安全な時代ではある
サピエンスの今後
→生物工学、サイボーグ工学、非有機的生命工学は今までの自然選択の代替となりえる
→(例えばどこまでが生体でどこからが機械なのだみたいなこと)
→その結果、サピエンスはいずれ特異点に至る
→今ある意義が意味を持たなくなる時点。人間の意識とアイデンティティの根幹が変化
→技術の使い方によりサピエンスの歴史に幕が下りるのかも
→(滅びということでなく、別の生物というか別の何かへということ。倫理的なことはおいとくと、例えば様々な動物の高い能力がある部分を移植した、ある部分の能力が突出して高い個人を作れるようになったら。機械的な装置も組み合わさったら)
下巻の各部分をもう少し。
神が全知全能の時代だったが、科学により人は無知だということを悟った。伝統的な記述より、観察結果を信頼するようになった。
ヨーロッパだけでなく中国にも大航海する技術はあった。実際に中国は鄭和(ていわ)という人物がアフリカ方面に遠征したが、政権が変わると遠征をやめてしまった。アメリカ大陸を発見し、それに対する好奇心と、現状維持で満足しなかったのがヨーロッパ覇権に繋がった。
覇権がスペインからオランダ、イギリスへと移り変わっていく内容が面白く読めました。
同時に資本主義の光と闇が共に書かれています。信用制度の中で、信頼を失った国家や組織は資本家から相手にされなくなっていく。日本も集団になると信頼に値しないというのが一般にまで知られてしまいましたが。
また、物質的に裕福になった現在、文明によって人間は幸せになったかを検証している。そうすると幸せとは何か、どう捉えればいいか。
幸福は客観的な条件、すなわち富や健康、さらにはコミュニティにさえも、それほど左右されないということだ。幸福はむしろ、客観的条件と主観的な期待との相関関係によって決まる。
上は、人は何を望んでいるかによって相対的に幸福だったり不幸だったりするということ。
科学的にみると、幸福感は単純にセロトニンやドーパミン、オキシトシンから決まってしまう。人間の生理的には昔と何も変わらないが、現在は脳内のセロトニン量などをコントロールできるというところが以前とは違っている。
(「ソーマ」という合成薬を飲み全ての人が幸せな「素晴らしい新世界」というディストピア小説がある。これを不穏に感じるが、誰もが常に幸せなのに、何が悪いのか。どこが問題か説明するのは難しい)
幸せには認知的、倫理的側面があり、人が持つ価値観次第で差がつく。苦労していても意義のある人生が幸せだという考え方もある。その場合、無意味な人生はどれだけ快適な環境に囲まれても試練に他ならない。
幸せとは自分の内にあるものだが、仏教では、それを求める気持ちは幸せとは対極のものだ。あるがままに受け容れるという仏教の話まで出てくる。(仏教ではいわゆる「ふーん状態」を目指すのかもw。片山まさゆきの「ムカフーン」から取りました。辛いことが色々重なって、最終的にキレてふーんと悟ったような境地)
というようなことを前提に、幸せとは何かを考察していく。この本は冷静に様々な観点から検証しているのがいいのだと思う。
最終章は未来の話でした。ここだけ読んでも面白い。
人の脳がインターネットと繋がって、例えば他人の記憶を自分の記憶や知識として検索・共有できたら、いったい各個人の意識などはどうなってしまうのだろう(インター・ブレイン・ネット)とか、そういう新しい可能性の話が幾つも書かれていました。
DNAによる差別なども考えておかなくてはならない。遺伝子操作にしても、倫理的には多分止められないだろうと。
それにしてもこういうのを読むと毎回思う、大航海時代のスペイン人の酷さよ。(コルテス、ピサロ)
-- 記事一覧ページへ --