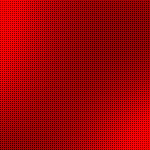出生数の減少も人口の減少も避けられないとすれば、それを前提としていくしかないであろう。求められている現実的な選択肢とは、拡大路線でやってきた従来の成功体験と決別し、戦略的に縮むことである。
そのためには多くの痛みを伴う改革が必要だが、まずは人口減少社会の実体を正しく知らなければならない。
人口減少につれ、これからどういうことが起きるか解説し、最後に「ではどう乗り切ればいいのか」という提言を幾つかしています。
少子化というか、老人ばかりになって病床も介護する人も足りず、どうすりゃいいのさこの私、夢は夜ひらくという未来が決定している。
国外から人を入れれば国のカタチが変わってしまう。そもそも人が来るほど魅力的な国ではなくなっている。
八方ふさがり八宝菜。
人口は減少でも世帯数が増えている。一人暮らしが増えちゃった。私もそうですし。てへ。
低負担なら低福祉。でも高負担でも中福祉くらいにしかならない。それなりの水準を求めるなら超高負担を受け入れなければならない。
東京は大丈夫。んなわけない、むしろビジネス中心の街づくりで介護の基盤整備が遅れている。そこは地方よりやばい。
(読書アウトプットの適当感がすごくて m(_ _)m)
「提言編」
貧乏老人が増える→老後生活にかかる費用を少なくすればよい→安い家賃で入れる高齢者向け住宅を整備する。空き屋などの活用。
「非居住エリアの明確化」
非居住エリアと居住エリアを分け、非居住エリアのインフラ整備は受益者負担。非居住エリアは大型農業や新産業を生み出す集積地とする。居住地域の拡大を続ければ、結局は生活できなくなる土地が広がるだけ。戦略的な国土の活用を。
これは「街のコンパクト化、徒歩範囲に必要施設を揃える」など自分も思っていますが、先祖代々のという人が難しい。
「社会保障費の循環制度」
例えば健康保険は3割負担。こういうものの残り(7割部分)を公で立て替えたと考えて、死後にその分を返還するという考え方を提言しています。
多くの人は資産を残して亡くなる。本人は生きてるうちに財産が減るわけではないですが、実質相続の取り分が減るということだから反発も多そう。
「セカンド市民制度」
定住人口ではなく、地域への訪問者(いわゆるファン)をセカンド市民とし、住民登録、第二の故郷、行政サービスはする、住民税は住民票のある自治体と按分など。
ふるさと納税の拡大版みたいな感じかな。
-- 記事一覧ページへ --