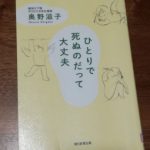初期の頃は先にオケをほぼ作成し、それに歌メロディを入れてから最後に歌詞を作ってました。
単純にパソコンで楽器の音が出せるのが自分にとって珍しく、一般的なコード進行を探して並べ、音源のプラグインを色々な音色でそのコードで出してみて、先にボーカルオフのカラオケを作成するイメージでした。
今は逆になり、先に歌メロと歌詞から作り始めるようになってます。どちらかというと歌詞からです。人によって様々なパターンがあるはずですが、現時点での自分の場合を整理しておきます。
(細かく書いていて長くなってるので悪しからず。まさに今DTMを始める、私より初心者がいれば参考になるかもしれませんが、いずれ自分なりのやり方になりますよね。)
1.歌詞
これはもうテーマを決めてChatGPTに渡し、ザクっと歌詞のアイデアを出してもらったり、1番だけ自分で作って、これこれのイメージなので2番を作ってみて、などと無茶ぶりします。
そうするとあれこれ出してくるので、「なるほどね」と思いながら、部分的にまるっともらったり、組み合わせたり差し替えたりとパズル的なことをして一応の仮の歌詞を作ります。
もちろん自分でも捻りだしますが、歌メロディを作る為のとりあえずの仮歌詞なのでChatGPTが8割を作ってます。主張したい事があれば、それを書く方がいいけど。
これをスルーしてオケを先に作成し、そのイメージから歌詞を作るでも良いのです。
2.歌メロディ
歌のメロディを作りたいのですが、それをやり易くするための準備が幾つかあるので順番に書いてみます。(全部仮でやっていて、後で戻って直したりします)
ここからDAW(音楽作成ソフトウェア)上の作業になります。
2-A コード作成
歌メロは無から鼻歌でもいいのですが、コードがあると先にスケール(Cメジャーとか)を決めることになり、メロディもそのスケールで作れたりと、後々楽な気がします。(スケールは後でボカロの声の音域に合わせて変更が必要になることもあります。)
コード進行を考えるのに幾つかの方法を用いているので列挙します。(考えるというかほぼ真似だけど。)
・今回作りたい雰囲気を考えて好きな既存曲から持ってくるパターン
コード進行をパクる。曲のコード譜を公開しているサイトで調べたり、曲の音声データがあれば解析したりできる。(完璧な解析とはいかないので要修正ですが)
・有名コード進行を並べるパターン
先ずは、私のような初級者が自分で新しくコード進行を生み出したと思っても既にあります。
ジャンルを選ぶとコードの並びを幾つか出してくれるプラグインソフトがあるので使う。
もちろんネットでカノン進行、丸サ進行等の有名な進行を調べたりする。(1563-4145、4536、6451等の数字で表したりして、たまにDTMをやるくらいでは忘れてしまう)
・歌詞をSuno AI(作曲AI)に入れてみて、良いなと思ったものから持ってくるパターン
これはメロディの気に入った部分も流用出来る。全部使ってもいいとは思うけど、その場合はAIがメロディを作ってしまうので、自作メロディ作りの楽しみが無くなり、DTM趣味としては楽器を乗せる編曲の部分の方を主に楽しむ感じになると思います。
(AIの編曲の一部分を参考にするのもあり。Sunoは課金した期間に作成したものは何処かに出しても良いという事に、現時点ではなっている)
その後、コード自体や進行に自分なりに手を入れてあちこち修正し、一応の完成としておく。(もちろん後で修正はあります)
編曲時はこのコードを元にルート音を下に加えたり転回系にしたりリズムを変えたり、各楽器でそれ用の実際に使う状態にする必要がありますが、多分その辺をしっかりやれば理論的な勉強になりそうな気がする。
2-B 構成を仮で決める
コード進行と同時になりますが、一応ここがAメロ、ここで間奏8小節などとザクっと決めておく。もちろん歌メロの具合でBメロを1小節伸ばすとか、色々が同時進行にはなります。
これでBPM(テンポ)によってですが、大まかに曲の長さの目安が分かってきます。
2-C 仮のドラムを入れる
イメージする曲からBPMを仮で設定し、今回作成したい雰囲気の曲に合いそうなドラムを入れてみる。ゆっくり、激しく、四打ちなど。
といっても今は音源にドラムパターンのプリセットがあるので、それを選んで並べるだけ。どうせ後で変更するので前の曲そのままでもいいし。
2-D 歌メロディを作成(作曲)
ここでいよいよ仮の歌詞を元にAメロ、Bメロ、サビの歌のメロディを作ってみる。ここがいわゆる作曲という事なのでしょうね。全工程を見るとほんの一部分ですが、重要なところですよね。
歌詞が未だ無い場合は、もちろんメロディだけ作ればいいけど、例えば既存曲の歌詞を借りて違うメロディ、リズムにしてみるとかも作りやすい。(最終的に全く別の歌詞を作ることになりますが)
私はDAWでピアノやシンセの音を使い歌メロを作りますが、いきなりボカロなど音声合成ソフト上でメロディ(歌詞も)を考えても良いです。(やり方は千差万別) 楽器の音をボカロに持っていくと全然イメージが違う場合があるので、歌詞があるならいきなりボカロソフト直の方がいいのかも。
またピアノだと音域を広くし過ぎてボカロの声が出ない(出るけど)とかになりがちなので、1オクターブ半程度とか最近は一応気を付けるようになりました。でも人が歌うのと違ってそれに囚われないのがボカロの良い所でもあるし、むしろ積極的にやるべきなのかもしれません。
(今は人が歌える想定で作ってますが、そういうのはプロの曲が無数にあるわけだし、普通に作るとボカロ好きな人も聴くわけでは無い。)
上の作業は、私の場合はコードとドラムがあると何となくのイメージが湧くので、それはこのフェイズの為にやったものです。何も無しでいきなり鼻歌でメロディを考えて、それをMIDIで打ち込んでいく人もいるはず。(その場合はコードを後で付けたりするはず)
3 ボカロ(音声合成ソフト)へ
メロディと歌詞を合わせて歌の状態にします。
上でピアノ等で作ったメロディをMIDIデータファイル化して、ボーカロイド等の音声合成ソフトに持っていく。私は今はSynthesizerVを使いがち。
誰の声か決めて、MIDIでインポートしたノートに歌詞を入力していく。歌詞を入れていくと高すぎるとか低すぎるとか思う場合があります。
全体的に歌声が丁度良くなるように半音ずらしながらサビの高音などを聞いてみて、実際のスケール(Cメジャー等)を決定します。(最初からちょうど良い声域の範囲内で作れればいいのですが。)
DAWに戻ったら作ってあったコードなど、音程が関わるものはその分ずらしておきます。
声色や歌い方などを調整。(これを「調声」というらしく、「チョウショウ」と読むらしい。最近まで「ちょうせい」だと思ってました…)
これは歌ものとしては最重要なのに、私が適当過ぎてやり始めたのはここ最近です。特にSynthesizerVだと、入力したままで結構良いなと思っちゃうので。
今よくよくSynthesizerVのソフトを見ると、Ver.2になったこともあるし、非常に細かく調整できるようになっています(何をいまさら言ってるんだか)
あと音声合成でなく、自分で歌える人は歌って録音するのも楽しいでしょうね。
そして歌だけのものを音声データ出力して、これをDAW(音楽作成ソフト)で取り込みます。この段階ではフルコーラス無くて雰囲気を見る為に1番だけ作ったとかもある。
(DAW内部からシームレスにSynthVを呼び出せるのですが、なるべくPCの動作が軽くなるよう使いたいのがあって分けて作業してる)
4.編曲(アレンジ)
ここまででDAWソフト上に歌とコードがある状態です。ここで歌メロ以外を全て作っていきます。上で作成した歌詞入り歌データがあると、MIDIのメロディと違って断然イメージがしやすくなります。
歌とコードを鳴らしながら(ドラムも)、とりあえずルート音でベースを入れ、それからはピアノを入れたりギターを入れたり、好きにやれって感じの工程。
バンドサウンドっぽくしたくてギターを入れて、なんか思ったような音にならないなあとか、最初から音源に含まれているプリセットなどもありますが、そもそも音作りが難しいです。
音源だけでなく、イコライザーやコンプレッサーなど、作った音を更に加工したりも出来ます。以前作成したギターの音が欲しければ、音声トラックの設定をそのままコピーして持って来られます。
シンセサイザーであれこれ弄ってみたり、楽器音源の色んな音色を聞いて、実際に使用する音を選んでいきます。
コードをバーンと鳴らすだけでもいいですが徐々に色々とやれるようになって来る。楽器はそもそもメロディやリフを考えるのもあるし、打ち込むMIDIも音の長さやタイミング、強弱(ベロシティ)を細かく調整しようと思えば幾らでも出来てしまう。
ということもあり、この編曲が趣味DTMの全工程で一番時間を使う所じゃないでしょうか。
もちろん歌詞や歌メロを良くしようとそこをずっとやってる場合もあるでしょうけど、私の場合はまだ全体的に練習をしていて、その辺をそこそこにして数をこなす段階です。
あと(サブスクでお金が必要なので)私はやらなくなってますが、Splice、Loopcloudなどからプロが作ったかっちょいいループ音源を持って来て、加工したり切り貼りしたりもしたい。素人はその方がクオリティが上がるはず。
5.MIDIを音声データに変換しておく
編曲中の話です。
パソコンを変えたりすると、認証が必要で音源などのプラグインソフトが動かなくなったりする可能性があります。DTMの環境を再構築するのは結構大変で、期間を決めて無料配布された音源などは使えなくなります。
そういう反省もあり(笑)、PCの動作も軽くなるし、適宜、音声データに変換(バウンス)しておくことに。
仕事じゃないので再現出来なくても良いのですが、後々やりやすいし、一応最終的には全てのトラックを音声データにすることにしました。
もちろん音声データに変換してから、面倒くせえと思いつつも(笑)MIDIに戻って修正し、再度音声データにという事も出てくるので、なるべくMIDIのままで保持したいのはあります。(でもPCの負担が重くなっていく)
6.ミックス、ミキシング
ある程度ざっくりは編曲時にやってますが、編曲が終了したら調整をします。この辺りで歌詞とかメロディとか、仮だったものは一応すべて確定しておきます。
この工程で何をするかというと、楽器毎に左右にパンを振ったり、音量のバランスを調整したりです。全体的なバランス調整です。
ただオートメーションという仕組みがあり、音量もフェーダー固定で調整するだけでなく、例えばAメロは小さい音で、サビは大きくなど、曲中での変化を付けたりします。プラグインの一つのボタンをオンオフをしたり、特定のタイミングでダイアルを回したり、細かい調整が自動で動かせたりします。
あと重要なのが高音楽器の不要な低音を削るとか、低音が重なってもこもこしてしまうので、その辺を調整したりだと思います。聴いていて高音で耳が痛いとかもあるため、そこを削ったり。歌が聞こえるように他の楽器を調整したりです。
とりあえず編曲がイマイチだったりは置いといて、最近は自分で何度か聴いたときに、耳が痛くなったりせず心地よく聞けることを目標にすればいいかなと思いました。
曲の出来以前に、聴いていて不快なのは問題外ですもんね。大変申し訳ございませんm(__)m
そんな事をしながら全体のバランスを整えて、聴きやすくしているつもりなのですが、これがヘッドホンによって聞こえ方がかなり違っていて、非常に混乱してしまう。
特にベースとか低音の出方がわけわからなくなってくる。「ベースが大きいなあ。小さくするか」。でも別のヘッドホンだと聞こえない…の繰り返し。
ここ数曲はまだしも、自作曲を聞いてみると流石に酷いバランスだったりで、どうして当時はそれでいいと思ったのかと思ってしまう。(直近の曲も1年後に聴くとそうかもしれません)
プロの曲ってスマホのスピーカーでもそれなりに良く聞こえるので、経験則で色々とあるのでしょう。自分で出来る事は可能な限り良い環境でも悪い環境でも試しに聴いて何度も調整してみるしかないのですかね。
なので全体を先ず普段よく音楽を聴いているヘッドホンで作り、低音を合わせるのはこのヘッドホンとか、高音の耳障りな部分をカットするのはこれ、などと決めておくと良さげ。
あとはリファレンスとなる曲を幾つか用意し、特定の楽器が同じくらいの音量になるように調整する方法があるようです。
またイコライザーを見ながら、極端にどこかの周波数帯域が出すぎてないかとかもチェックすると良さげ。
(なのですが、忘れていてやらなかったり…)
そんな感じで、やればやる程に新しい事を覚えてやることが増え時間もかかります。
それでネットにアップしても大して聴かれないのだからアレですが、結局は自分がやってて楽しいんだからいいんじゃないのというメンタルになっていきます。
(でも多く再生されたいという野望も忘れてはいけないはず。多分)
7.マスタリングというか最終工程
ミックスして一応はバランスが整い、聴きやすくなったとしましょう。
最終的には音声データファイルとして出力しますが、その前に音量バランスや音圧などを調整し、ネットに上げた時に聞こえ方にバラツキが無いようにします。(プロだとCD、アルバム内の曲の質が一定になるように等)
プラットフォーム毎にLUFS値というのが定められていて、人が聴いた時の聴感を合わせるようになっています。(知った時にそれが-14だというのでクソ真面目に合わせていたら音が小さすぎてしょぼい。今は-9、-10くらいにしてます)
音を大きめにしても各プラットフォームの基準に合わせて調整されてしまいますが、小さい音を大きくしてはくれないので、音が小さいよりは少し大きめな方が良い感じで聞こえるようです。
YouTubeで音が小さな動画だなーってのありますよね。そうならないようにということ。
あと音圧というか、曲の音が小さい部分を持ち上げてある程度均一にしたり。音の大小のダイナミックレンジを広くとる考え方もありますが、クラシックだとレンジが広くてボリュームを上げないと音の小さな部分が聞こえないので、そういう部分を無くすなど。
またピークが音割れしないようにリミッターをかましたりです。
8.WAVファイル作成
そして最終的な音声データファイルを出力。WAVやmp3等にします。基本的にWAV形式の方が音が良いですがファイルサイズが大きくなります。
前後の余白とかどれくらいが良いんでしょうね。これを書くまで自分なりにやってましたが、そういえば調べた事は無かった。
全ての楽器や音をまとめて出力することになるので、打ち込んだMIDIのままやってると、非力なマシンだとフリーズしたりすることもあります。
なのでMIDIで打ち込んだ各楽器トラックを音声データに変換しPCの負荷を軽くしておく方が、全体的にスムーズで良いと考えてます。
そして完成!
9.MV作成
DTMとしては上記で終了ですが、ボカロ関係だとMusic Videoを作りたいですよね~。動画用の一枚絵を外部発注したり、動画作成を外部に委託する方法もあるようですが、私みたいにそこまで拘らず自作の人は多いはず。
自分で動画を作るのも創作趣味として楽しいですし、でもいつか上手な人に作って貰いたい気持ちもあります。
先ず、上で作成済みのWAVファイルを動画作成ソフトの方に持っていきます。
そしてどういう感じに作ろうかなーと考えながらネットで画像を探したり、著作権的な問題がどうなるのかと思いながらAI画像を出力してみたりします。
画像を配置して、歌詞をタイミングを合わせて入力し、エフェクトなどをあれこれすればMVの完成です。もちろん歌詞は無しでもいいし、正解は無いので好きなように作ればokです。
出来たーと思ってネットにアップすると、妙な達成感があります。
以上です。
—–
例えばですが、どの段階でもここを修正したいと思ったら、そこに戻ってボカロで歌詞を入れ直したり、自分だけでやってると何時でも好きな部分に戻って修正出来ます。
複数人でやっていたら複数であーだこーだ作る楽しみがあると思いますが、あまり自分の意見を通し過ぎたり、完成の期日があると中々そういうのは難しい場合がありますよね。
あと、あるあるとして初期は既存の曲と似てしまったりを異常に恐れますが、そういうのはある程度再生されたりしてから心配することな気がするし、そもそも初心者が既存曲のアレンジを高い質で再現するのは難しいです。
歌メロや印象的なリフ等が似てしまうのは避けたいですが、確率的に一部は似ても歌メロが丸々そっくりにはならないだろうし、他はそんなに気にしなくても良いのでは。
という事で趣味のDTMの現状のまとめですが、軽い気持ちで書き始めたら長くなりました。さすがにここまで読んでくれた人は少ないとは思いますが、ここを見ているという事は、マジ感謝(ギャルか)
ついでに私のYouTubeチャンネルでも見ていってください。
-- 記事一覧ページへ --